9.独立学園との懇談会
無教会と独立学園
中村 頌
プロフィール
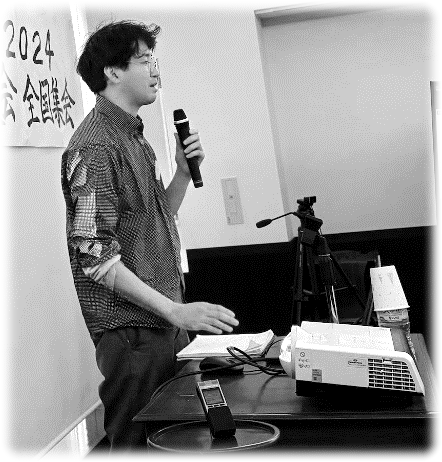 1988年生れ。東京大学大学院教育学研究科卒業。専門は教育哲学。
1988年生れ。東京大学大学院教育学研究科卒業。専門は教育哲学。
2013年より基督教独立学園高等学校に勤務。英語科、聖書科を担当。2024年より同校教頭。
はじめに
独立学園で教員をしている中村頌(しょう)といいます。私は以前から、無教会全国集会に「現地参加」できないかを模索していました。オンラインでの参加も悪くはない、けれどできることなら是非今井館に足を運びたい、そう思っていました。なぜ現地での参加にこだわっていたのかといえば、それは私の個人的願いというよりも、ある「予感」に基づくものでした。その予感とは、「無教会の方々と顔と顔を合わせ関わることが、独立学園の教育実践において本質的な重要性をもつのではないか」というものです。今回幸いにも、学校の予定と重ならず、3名の生徒と共に今井館を訪れることが叶いました。また、一参加者として列席が許されたのみならず、昼休みの時間に有志の懇談会の場を設定していただきました。本校を紹介する機会、そして無教会のみなさんと交流する機会を賜りましたこと、感謝いたします。
この記録のための文章は、現地参加した3名の独立学園生と共に、集会を振り返って執筆しました。以下の4つの文章をもって、今回の懇談会の記録と代えさせていただきます。内容は、現地での発表と被るものもあれば被らないものもあります。「1」は、生徒による独立学園の簡単な紹介です。「2」は、懇談会で話した内容のうち最もお伝えしたかった点に絞って紹介します。「3」および「4」は、どのような思いをもって無教会全国集会に参加したのか、そこでどのような学びがあったのかについて、二人の生徒が記しています。
1. 独立学園紹介「山形県の小さな学校」(2年 森芭奈)
2. 「地下水としての無教会精神、そして独立学園」(中村頌)
3. 無教会全国集会に参加して①「見えないものを見る」(2年 岡槻之介)
4. 無教会全国集会に参加して②「ほんとうの平和を知る」(1年 西川恵祐)
とりわけ、生徒が書いた文章を読んでいただくことで、本校で学び育っている若い魂の息遣いを感じていただければ幸いです。なお、現地参加をした3名のほかに、オンラインで集会に参加した生徒が5人います。本校生徒の無教会への関心の高さを感じていただけるのではないかと思います。
1. 独立学園紹介「山形県の小さな学校」(2年 森芭奈)
基督教独立学園高等学校は、一学年25人を定員とする少人数制の学校です。一般の高校と同じ授業カリキュラムに加えて聖書や英語讃美歌などの授業がありますが、普通科の学校です。1948年、内村鑑三先生の弟子の鈴木弼美先生によって創立され、76年続いています。現在は第三学年(75期生)が22人、第二学年(76期生)が15人、第一学年(77期生)が21人の計58人と、キャンパス内に住む教職員の先生とともに生活しています。
独立学園は、「読むべきものは聖書、学ぶべきものは天然、為すべきことは労働」という内村先生の言葉を三本柱として掲げています。「為すべきことは労働」に基づいて学園生は日々の授業に加え、農作業や牛・豚の世話、牧草の刈り取り、トイレの汲み取りまで行っています。植物の種蒔き、発芽、成長、収穫、堆肥生産まで、また牛・豚の誕生から解体に運ぶまでといった一般の高校生が体験しない、動植物の始めから終わりまでを学びます。
独立学園では、毎日朝拝・夕拝を行い、そのなかにある「感話」という機会を通して自分の思いを話します。キリスト教信仰が強要されることはありませんが、真面目に聖書を学ぶことが学園生活の中心です。また、平和についての学びも活発です。講師をお招きし、話を聞く機会や、憲法についての勉強の機会もあります。
また学園生は、入学時に「契約の書」により8つのことを約束し、それを日常生活でも大切にしています。他にも対話や自分たちで作り上げていくことも大切にしています。スマホやインターネットを通してではなく、今目の前にいる人と目を見て話すことは、現代社会でも出来なくなってきているからこそ続けていきたいものの一つです。また独立学園では、行事や部活など自分たちで何かを作り上げることが多いです。特に三年次の修学旅行では、行き先から訪問施設、食事、交通手段などすべて自分達で決め、予約や連絡も自分達で行います。
そうした多くの特色がある独立学園ですが、信仰の立場としては、どの既成のキリスト教の教派にも属さず、内村鑑三先生が唱えた自由と独立を尊ぶ無教会の立場に立ち、聖書が指し示す正義と平和の道を求めつつ歩んでいます。
そのような独立学園と深く関係する無教会の全国集会に参加することができて良かったです。また、普段は聞く機会がないようなお話を聞くことができて勉強になりました。ありがとうございました。
2. 「地下水としての無教会精神、そして独立学園」(中村頌)
全国集会に参加するにあたって、無教会についての勉強会を独立学園で企画しました。参加希望の生徒10名が集まり、「無教会とは何か」と題された文章(矢内原忠雄著)を読みながら、率直にまた真剣に感想や疑問を出し合いました。そのなかで一人の生徒が、テキストの文章について「気になる点」を挙げてくれたのですが、そのことについて紹介させてください。その発言は、無教会にルーツをもつ本校の存在意義について、大きな示唆を与えるものでした。
矢内原は先の文章のなかで次のように書いています。「エレミヤとイエスのあいだには600年の経過があるが、エレミヤの宗教改革の精神が地下水となって、イエスのところでまた噴出した」。無教会についての説明のなかで、矢内原はその源流を旧約の預言者エレミヤに見ます。無教会とは、決して内村による創建ではなく、旧約の預言者から脈々と引き継がれている精神性を指すというのです(これは内村鑑三自身の理解とも重なります)。先の文章で、矢内原は具体的人物として「エレミヤ」「イエス」「パウロ」「ルター」「内村鑑三」の名をあげながら、無教会の系譜を説明しています。そしてこの系譜につらなる5人を、地下水の「噴出点」として形容しました。「エレミヤの宗教改革の精神が地下水となって、イエスのところでまた噴出した」。そして地下水はその後、パウロにおいて、またルターにおいて、そして遂には内村鑑三において湧き出たというのです。
今回の勉強会で、一人の生徒がこの「地下水」という言葉に注目しました。この表現の何が、生徒の関心を引き起こしたのでしょうか。彼女は次のように説明しました。
「地下水という言葉から、私はある「流れ」をイメージするんです。ここで書かれて
いることは、目に見えるかたちで地上に噴出してはいない間でも、流れ続け、受け継がれて
いるものがある、ということなのだと思います」
この女子学生の感想は私の心に、ある種の感動をともなったインスピレーションを与えました。「地下水」という、目に見えないところで受け継がれていく「流れ」。このイメージによって私が知らされたのは、遥かな過去からまだ見ぬ将来へとつづく不断のつながりのうちに「私」がいること、そして無教会があるということです。少しだけ説明させてください。
矢内原は、無教会の精神的系譜をたどるにあたって、エレミヤ、イエス、パウロ、ルター、内村鑑三の名を挙げました。言うまでもなく、歴史に名を刻む傑物たちです。私たちはこれらの偉大な先達を、いのちの水の噴出点として記憶しています。しかしその水は、何もないところから、突如吹き出してきた「魔法の水」ではありません。この水は「地下水」として、どの時代においても変わらず伏流してきた。言い換えれば、先の5人の間隙に、この水を地下深くにおいて時代から時代へと繋いでいった担い手がいたということです。そして、さらにこうも言えます。旧約の時代から脈々と続く無教会精神としての「地下水」は、「内村鑑三」という噴出点をもって完結したのではない。途絶えたのでもない。そうではなく、私たちが生きる今なお流れ続けている。それは、人里離れた場所で湧水として、ひっそりと大地を潤しているだけかもしれません。あるいは、しばらくは地表には現れないものかもしれません。しかしそのいずれにしても、この精神は、はるか過去から受け継がれてきたように、いつかまた噴出する「とき」を待ちつつ、今もこれからも継承されていく。地下水として、歴史の表舞台からは見えない場所で、確かに底流し続ける。私にはそう思えてなりませんでした。
このようなイメージの何が、私に深い感動を与えたのでしょうか。それは、私が勤めている基督教独立学園の教育の営みがまさにこの「地下水」の働きにほかならないと思ったからです。時代から時代へと静かに受け継がれるものがある。独立学園はその水脈の一端を、恐れ多くも担わせてもらっている。その地下を流れる水を「無教会精神」と呼ぶことが許されるのであれば、その精神は、担い手や現れ方を代えつつも、なお私たちの学校のなかに息づいています。静かに、でも確かに、日々の生活の営みや教育のわざのうちに、この地下水が流れていることを感じるのです。時代のこの大きな変化のただなかにあって。
無教会精神を次の世代につないでくださった一人一人の先達たちのおかげで、今の独立学園があります。深い感謝の意を表したいと思います。そして私たちの学校が神様から与えられた使命を、今後も変わらず担っていくことができるよう、祈りに覚えていただければ幸いです。
3. 無教会全国集会に参加して①「見えないものを見る」(2年生 岡槻之介)
無教会全国集会への参加を決めた理由は、ある一人の方に「あなたの学校と深く関わりがあるのだから」と内村鑑三さんについて学ぶことをすすめられたからでした。それから興味がわき少しずつ内村さんについての本を読むようになりました。そのなかで無教会という立ち方をしっかりと学びたいと思いました。全国集会での三人の方の講演を聞かせてもらい感じたことや考えたことについて書こうと思います。
月本さんの聖書講話のなかで「旧約聖書や新約聖書のなかには沈黙が存在する」ということをおっしゃっていました。私はそのお話の後に「沈黙している」ということについて詳しく教えて頂きました。返答をうけて考えたことは、読むさいに聖書を単なる情報として読んではならないということと、聖書の内容を「理解すること」と「信仰すること」は似て非なるものだということです。「聖書のなかにはあえて書かれていないことや知らされていない部分が多くある。だからこそ、その語られていない空白(沈黙)に目を向けて読む必要がある」と月本さんはおっしゃいました。単なる活字としてではなく、そこに隠されている言葉に目を向けなくてはならないと語られ、僕はこれまで情報として聖書を理解していたのかもしれないと気付かされました。
またヒョン・ヒャンシルさんが語られた、在日朝鮮人の歴史と今の現実についてのお話が印象に残っています。不平等や格差があるというヒョンさんの語られた日本の「現実」は、日本人として生きている私にとって向き合わなければならないことだと、強くつきつけられました。
集会のテーマであった「ほんとうの平和とは」と向き合うなかで、とても重要なメッセージを与えてもらいました。私たちはしばしば知らなかった情報に出会うことがあります。そのような情報に出会ったとき、私は知ったことを疑い、認められないことがあります。自分のプライドが邪魔をするのです。このことは必ずしも「情報」だけにとどまらず、「人」とも言い換えられると思います。だからこそ私は、この不平等な社会をつくり出しているのは自分かもしれないと感じました。そしてだからこそ、自分と違う人や情報に謙虚でありたいと思いました。この戦乱の世界を前にしてたくさんの方々と同じ場所に集い、平和に思いを寄せることができたことに心から感謝しています。
4. 無教会全国集会に参加して②「ほんとうの平和を知る」(1年生 西川恵祐)
私にとってキリスト教は「居場所」です。両親がクリスチャンで、生まれたときから教会にかよっていた私にとって、キリスト教は居場所であり、家族でした。
今、私が在学している学校、基督教独立学園は聖書、天然、労働を大切にする学校です。その中でも聖書は、私がこの高校を受験することを決める上で一番大きな理由でした。学園で聖書を同年代のクリスチャンやそうではない人と勉強するうちにキリスト教に対する疑問が次々に生まれました。その疑問と向き合い、考えることには恐れや不安がありました。15年間自分の考え方と常に一緒にいた家族同然のものが、崩れかけているように感じたからです。そんな中、今回の無教会の全国集会のことを聞き、事前の学習で自分の考えを得るヒントになるのではないかと考え、参加させていただきました。
講演をお聞きして、求めていた以上の学びを得ることができました。月本先生が話してくださった旧約聖書の民族主義の話と今とのつながり。榎本先生が話してくださった伊江島で戦った方々の強さと美しさ。そして玄先生が話してくださった“別の記憶”で見た朝鮮と日本の歴史。そのどれもが貴重な学びとなりました。講演を聞きながら歴史を知り、過ちを知り、自分の無知を痛感しました。キリスト教と今の世の中に疑問を持ち、平和を求めていながら、無知で無責任な自分を知りました。私はまだ、今回の講演に対して自分の考えを持つことができていませんが、玄先生の講演の最後に「関心を持て。関心を持ったなら動け。」とおっしゃっていたように、私も考えを深めることをやめずに自分の考えを持ち、明日の平和のために行動していきます。
今回の経験で求めていた疑問の答えは出すことはできませんでしたし、新しい疑問も増えましたが、求めていた以上の学びを得ることができました。今回の集会のテーマである「ほんとうの平和」についても私はまだ答えがわかりませんが、「知ることが平和への大きな一歩になること」を知ることができました。今回の私の一つの大きな学びです。このような学びが得られた恵みに感謝します。ありがとうございます。

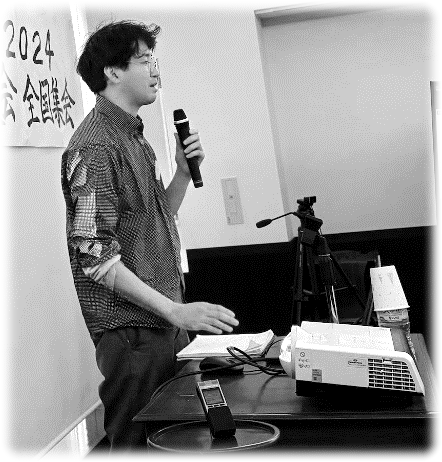 1988年生れ。東京大学大学院教育学研究科卒業。専門は教育哲学。
1988年生れ。東京大学大学院教育学研究科卒業。専門は教育哲学。2013年より基督教独立学園高等学校に勤務。英語科、聖書科を担当。2024年より同校教頭。
はじめに
独立学園で教員をしている中村頌(しょう)といいます。私は以前から、無教会全国集会に「現地参加」できないかを模索していました。オンラインでの参加も悪くはない、けれどできることなら是非今井館に足を運びたい、そう思っていました。なぜ現地での参加にこだわっていたのかといえば、それは私の個人的願いというよりも、ある「予感」に基づくものでした。その予感とは、「無教会の方々と顔と顔を合わせ関わることが、独立学園の教育実践において本質的な重要性をもつのではないか」というものです。今回幸いにも、学校の予定と重ならず、3名の生徒と共に今井館を訪れることが叶いました。また、一参加者として列席が許されたのみならず、昼休みの時間に有志の懇談会の場を設定していただきました。本校を紹介する機会、そして無教会のみなさんと交流する機会を賜りましたこと、感謝いたします。
この記録のための文章は、現地参加した3名の独立学園生と共に、集会を振り返って執筆しました。以下の4つの文章をもって、今回の懇談会の記録と代えさせていただきます。内容は、現地での発表と被るものもあれば被らないものもあります。「1」は、生徒による独立学園の簡単な紹介です。「2」は、懇談会で話した内容のうち最もお伝えしたかった点に絞って紹介します。「3」および「4」は、どのような思いをもって無教会全国集会に参加したのか、そこでどのような学びがあったのかについて、二人の生徒が記しています。
1. 独立学園紹介「山形県の小さな学校」(2年 森芭奈)
2. 「地下水としての無教会精神、そして独立学園」(中村頌)
3. 無教会全国集会に参加して①「見えないものを見る」(2年 岡槻之介)
4. 無教会全国集会に参加して②「ほんとうの平和を知る」(1年 西川恵祐)
とりわけ、生徒が書いた文章を読んでいただくことで、本校で学び育っている若い魂の息遣いを感じていただければ幸いです。なお、現地参加をした3名のほかに、オンラインで集会に参加した生徒が5人います。本校生徒の無教会への関心の高さを感じていただけるのではないかと思います。
1. 独立学園紹介「山形県の小さな学校」(2年 森芭奈)
基督教独立学園高等学校は、一学年25人を定員とする少人数制の学校です。一般の高校と同じ授業カリキュラムに加えて聖書や英語讃美歌などの授業がありますが、普通科の学校です。1948年、内村鑑三先生の弟子の鈴木弼美先生によって創立され、76年続いています。現在は第三学年(75期生)が22人、第二学年(76期生)が15人、第一学年(77期生)が21人の計58人と、キャンパス内に住む教職員の先生とともに生活しています。
独立学園は、「読むべきものは聖書、学ぶべきものは天然、為すべきことは労働」という内村先生の言葉を三本柱として掲げています。「為すべきことは労働」に基づいて学園生は日々の授業に加え、農作業や牛・豚の世話、牧草の刈り取り、トイレの汲み取りまで行っています。植物の種蒔き、発芽、成長、収穫、堆肥生産まで、また牛・豚の誕生から解体に運ぶまでといった一般の高校生が体験しない、動植物の始めから終わりまでを学びます。
独立学園では、毎日朝拝・夕拝を行い、そのなかにある「感話」という機会を通して自分の思いを話します。キリスト教信仰が強要されることはありませんが、真面目に聖書を学ぶことが学園生活の中心です。また、平和についての学びも活発です。講師をお招きし、話を聞く機会や、憲法についての勉強の機会もあります。
また学園生は、入学時に「契約の書」により8つのことを約束し、それを日常生活でも大切にしています。他にも対話や自分たちで作り上げていくことも大切にしています。スマホやインターネットを通してではなく、今目の前にいる人と目を見て話すことは、現代社会でも出来なくなってきているからこそ続けていきたいものの一つです。また独立学園では、行事や部活など自分たちで何かを作り上げることが多いです。特に三年次の修学旅行では、行き先から訪問施設、食事、交通手段などすべて自分達で決め、予約や連絡も自分達で行います。
そうした多くの特色がある独立学園ですが、信仰の立場としては、どの既成のキリスト教の教派にも属さず、内村鑑三先生が唱えた自由と独立を尊ぶ無教会の立場に立ち、聖書が指し示す正義と平和の道を求めつつ歩んでいます。
そのような独立学園と深く関係する無教会の全国集会に参加することができて良かったです。また、普段は聞く機会がないようなお話を聞くことができて勉強になりました。ありがとうございました。
2. 「地下水としての無教会精神、そして独立学園」(中村頌)
全国集会に参加するにあたって、無教会についての勉強会を独立学園で企画しました。参加希望の生徒10名が集まり、「無教会とは何か」と題された文章(矢内原忠雄著)を読みながら、率直にまた真剣に感想や疑問を出し合いました。そのなかで一人の生徒が、テキストの文章について「気になる点」を挙げてくれたのですが、そのことについて紹介させてください。その発言は、無教会にルーツをもつ本校の存在意義について、大きな示唆を与えるものでした。
矢内原は先の文章のなかで次のように書いています。「エレミヤとイエスのあいだには600年の経過があるが、エレミヤの宗教改革の精神が地下水となって、イエスのところでまた噴出した」。無教会についての説明のなかで、矢内原はその源流を旧約の預言者エレミヤに見ます。無教会とは、決して内村による創建ではなく、旧約の預言者から脈々と引き継がれている精神性を指すというのです(これは内村鑑三自身の理解とも重なります)。先の文章で、矢内原は具体的人物として「エレミヤ」「イエス」「パウロ」「ルター」「内村鑑三」の名をあげながら、無教会の系譜を説明しています。そしてこの系譜につらなる5人を、地下水の「噴出点」として形容しました。「エレミヤの宗教改革の精神が地下水となって、イエスのところでまた噴出した」。そして地下水はその後、パウロにおいて、またルターにおいて、そして遂には内村鑑三において湧き出たというのです。
今回の勉強会で、一人の生徒がこの「地下水」という言葉に注目しました。この表現の何が、生徒の関心を引き起こしたのでしょうか。彼女は次のように説明しました。
「地下水という言葉から、私はある「流れ」をイメージするんです。ここで書かれて
いることは、目に見えるかたちで地上に噴出してはいない間でも、流れ続け、受け継がれて
いるものがある、ということなのだと思います」
この女子学生の感想は私の心に、ある種の感動をともなったインスピレーションを与えました。「地下水」という、目に見えないところで受け継がれていく「流れ」。このイメージによって私が知らされたのは、遥かな過去からまだ見ぬ将来へとつづく不断のつながりのうちに「私」がいること、そして無教会があるということです。少しだけ説明させてください。
矢内原は、無教会の精神的系譜をたどるにあたって、エレミヤ、イエス、パウロ、ルター、内村鑑三の名を挙げました。言うまでもなく、歴史に名を刻む傑物たちです。私たちはこれらの偉大な先達を、いのちの水の噴出点として記憶しています。しかしその水は、何もないところから、突如吹き出してきた「魔法の水」ではありません。この水は「地下水」として、どの時代においても変わらず伏流してきた。言い換えれば、先の5人の間隙に、この水を地下深くにおいて時代から時代へと繋いでいった担い手がいたということです。そして、さらにこうも言えます。旧約の時代から脈々と続く無教会精神としての「地下水」は、「内村鑑三」という噴出点をもって完結したのではない。途絶えたのでもない。そうではなく、私たちが生きる今なお流れ続けている。それは、人里離れた場所で湧水として、ひっそりと大地を潤しているだけかもしれません。あるいは、しばらくは地表には現れないものかもしれません。しかしそのいずれにしても、この精神は、はるか過去から受け継がれてきたように、いつかまた噴出する「とき」を待ちつつ、今もこれからも継承されていく。地下水として、歴史の表舞台からは見えない場所で、確かに底流し続ける。私にはそう思えてなりませんでした。
このようなイメージの何が、私に深い感動を与えたのでしょうか。それは、私が勤めている基督教独立学園の教育の営みがまさにこの「地下水」の働きにほかならないと思ったからです。時代から時代へと静かに受け継がれるものがある。独立学園はその水脈の一端を、恐れ多くも担わせてもらっている。その地下を流れる水を「無教会精神」と呼ぶことが許されるのであれば、その精神は、担い手や現れ方を代えつつも、なお私たちの学校のなかに息づいています。静かに、でも確かに、日々の生活の営みや教育のわざのうちに、この地下水が流れていることを感じるのです。時代のこの大きな変化のただなかにあって。
無教会精神を次の世代につないでくださった一人一人の先達たちのおかげで、今の独立学園があります。深い感謝の意を表したいと思います。そして私たちの学校が神様から与えられた使命を、今後も変わらず担っていくことができるよう、祈りに覚えていただければ幸いです。
3. 無教会全国集会に参加して①「見えないものを見る」(2年生 岡槻之介)
無教会全国集会への参加を決めた理由は、ある一人の方に「あなたの学校と深く関わりがあるのだから」と内村鑑三さんについて学ぶことをすすめられたからでした。それから興味がわき少しずつ内村さんについての本を読むようになりました。そのなかで無教会という立ち方をしっかりと学びたいと思いました。全国集会での三人の方の講演を聞かせてもらい感じたことや考えたことについて書こうと思います。
月本さんの聖書講話のなかで「旧約聖書や新約聖書のなかには沈黙が存在する」ということをおっしゃっていました。私はそのお話の後に「沈黙している」ということについて詳しく教えて頂きました。返答をうけて考えたことは、読むさいに聖書を単なる情報として読んではならないということと、聖書の内容を「理解すること」と「信仰すること」は似て非なるものだということです。「聖書のなかにはあえて書かれていないことや知らされていない部分が多くある。だからこそ、その語られていない空白(沈黙)に目を向けて読む必要がある」と月本さんはおっしゃいました。単なる活字としてではなく、そこに隠されている言葉に目を向けなくてはならないと語られ、僕はこれまで情報として聖書を理解していたのかもしれないと気付かされました。
またヒョン・ヒャンシルさんが語られた、在日朝鮮人の歴史と今の現実についてのお話が印象に残っています。不平等や格差があるというヒョンさんの語られた日本の「現実」は、日本人として生きている私にとって向き合わなければならないことだと、強くつきつけられました。
集会のテーマであった「ほんとうの平和とは」と向き合うなかで、とても重要なメッセージを与えてもらいました。私たちはしばしば知らなかった情報に出会うことがあります。そのような情報に出会ったとき、私は知ったことを疑い、認められないことがあります。自分のプライドが邪魔をするのです。このことは必ずしも「情報」だけにとどまらず、「人」とも言い換えられると思います。だからこそ私は、この不平等な社会をつくり出しているのは自分かもしれないと感じました。そしてだからこそ、自分と違う人や情報に謙虚でありたいと思いました。この戦乱の世界を前にしてたくさんの方々と同じ場所に集い、平和に思いを寄せることができたことに心から感謝しています。
4. 無教会全国集会に参加して②「ほんとうの平和を知る」(1年生 西川恵祐)
私にとってキリスト教は「居場所」です。両親がクリスチャンで、生まれたときから教会にかよっていた私にとって、キリスト教は居場所であり、家族でした。
今、私が在学している学校、基督教独立学園は聖書、天然、労働を大切にする学校です。その中でも聖書は、私がこの高校を受験することを決める上で一番大きな理由でした。学園で聖書を同年代のクリスチャンやそうではない人と勉強するうちにキリスト教に対する疑問が次々に生まれました。その疑問と向き合い、考えることには恐れや不安がありました。15年間自分の考え方と常に一緒にいた家族同然のものが、崩れかけているように感じたからです。そんな中、今回の無教会の全国集会のことを聞き、事前の学習で自分の考えを得るヒントになるのではないかと考え、参加させていただきました。
講演をお聞きして、求めていた以上の学びを得ることができました。月本先生が話してくださった旧約聖書の民族主義の話と今とのつながり。榎本先生が話してくださった伊江島で戦った方々の強さと美しさ。そして玄先生が話してくださった“別の記憶”で見た朝鮮と日本の歴史。そのどれもが貴重な学びとなりました。講演を聞きながら歴史を知り、過ちを知り、自分の無知を痛感しました。キリスト教と今の世の中に疑問を持ち、平和を求めていながら、無知で無責任な自分を知りました。私はまだ、今回の講演に対して自分の考えを持つことができていませんが、玄先生の講演の最後に「関心を持て。関心を持ったなら動け。」とおっしゃっていたように、私も考えを深めることをやめずに自分の考えを持ち、明日の平和のために行動していきます。
今回の経験で求めていた疑問の答えは出すことはできませんでしたし、新しい疑問も増えましたが、求めていた以上の学びを得ることができました。今回の集会のテーマである「ほんとうの平和」についても私はまだ答えがわかりませんが、「知ることが平和への大きな一歩になること」を知ることができました。今回の私の一つの大きな学びです。このような学びが得られた恵みに感謝します。ありがとうございます。
